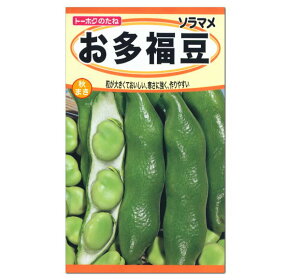◎前回の記事はこちら
【ソラマメ】種まきの前に吸水は必要?吸水あり/なしで発芽率を比較してみよう!(後編) - アタマの中は花畑
事前吸水の有無による発芽率の違いを比較していた我が家のソラマメ。その後は家庭菜園の片隅に植え替えて育てています。ソラマメの栽培は今年で2回目になるのですが、今回初めて摘芯と呼ばれる作業に挑戦してみようと思います。ソラマメを栽培するにあたりよく聞かれる摘芯ですが、この作業にはどのような意味があるのでしょうか?
摘芯とは?
摘芯(摘心・てきしん)とは植物の手入れの一つで、枝や茎の先端を摘み取ることを指します。摘芯を行うことにより脇枝や脇芽の成長が促されるため、開花する花の数を増やしたり、株全体の葉のボリュームを増やしたりする効果があります。ソラマメに限らず多くの植物に対して行われる作業で、ピンチや芯止めと呼ぶこともあります。
ソラマメの摘芯を行うのはなぜ?
ソラマメに関しては、摘芯を行うことで脇芽を多く伸ばし、結果として花や実の数(=収穫量)を増やす効果があります。茎の先端を摘み取るだけで収穫量が増えるのであれば、試してみる価値は十分ありそうですね。
昨年の私もそうでしたが、もちろん摘芯を行わなくてもソラマメの実を収穫することができます。ただ、植物には元々「主茎の成長を優先し、脇芽の成長は後回しにする性質」があるため、この場合は主茎のみが大きく成長することになります。もちろん、花や実が付くのも主茎1本が中心となるため、摘芯により複数の脇芽を伸ばして結実させた方が結果として収穫量は多くなると考えられます。
なお、摘芯の適期はちょうど今頃(11〜12月頃)のようです。摘芯の時期が大きく遅れると花芽にも影響を及ぼすため、かえって収穫量が落ちてしまうため注意が必要です。
まず1回目の摘芯をしてみよう!
摘芯について一通り触れたところで、早速我が家のソラマメも摘芯することにしましょう。ソラマメの摘芯は①1回のみ行う場合、②2回に分けて行う場合の2通りがあるようですが、今回は後者(②)で試してみたいと思います。
摘芯前のソラマメがこちらです。最近の強風に煽られまくっていますが、草丈は10〜15cmほどになりました。

株元をよく見ると、脇芽が少し顔を出していることがわかります。摘芯を行うことにより、今後はこの脇芽を伸ばしていくことになります。

摘芯を2回に分けて行う場合、1回目は赤線、2回目は青線のあたりで摘み取ります。それぞれの摘芯の目的は以下のとおりです。

◼︎1回目の摘芯(赤線)
・今回の記事でご紹介するものです。主茎の先端を摘み取り、根元から伸びる脇芽の成長を促します。
・脇芽が十分に伸びていない状態で根元から摘み取ってしまうと、葉が少なく十分な光合成が行えなくなります。そのため、主茎は先端のみ摘み取り、葉を数枚残しておくようにします。
◼︎2回目の摘芯(青線)
・1回目の摘芯から1カ月ほど経過したところで実施します。今後は脇芽のみを伸ばしていくため、不要になった主茎を根元から摘み取ります。
・この段階になれば脇芽が十分に伸びているはずなので、主茎を根元から摘み取っても問題ありません。
ということで、1回目の摘芯を行ってみました。少々勿体無いような気もしましたが、全ては来年春の収穫のためです。きっと元気な脇芽が伸びてくるはずなので、思い切って全ての主茎を摘み取りました。
1回目の摘芯を終えた株がこちらです。このまま1カ月ほど様子を見て、脇芽が伸びてきたら2回目の摘芯に踏み切る予定です。
◎次回の記事はこちら
【ソラマメ】1回目の摘芯その後〜2回目の摘芯に挑戦!〜 - アタマの中は花畑