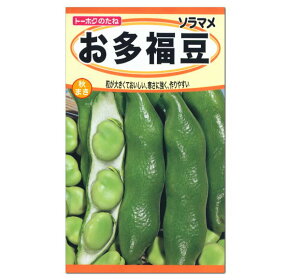悪天候続きで家庭菜園の手入れが全くできていないところですが…ようやくソラマメの種まきに着手することにしました。昨年同様、今年も実家から種を譲ってもらいました。

さて、種まき直前の処理といえば「吸水」を思い浮かべるのですが、吸水のあり/なしで発芽率に違いは見られるのでしょうか?今回はこちらのソラマメの種を使って比較してみたいと思います。
ソラマメの種に吸水は必要?
まず、ソラマメの種の吸水について調べてみたのところ、以下のような意見が見つかりました。
「ソラマメの種は大きいので吸水は必要!」
「吸水させずに種をまいても発芽します!」
「水分を与え過ぎると種が腐るので注意!」
もしかしたら全ての意見が1つの答えに行き着くのかもしれませんが…私のリサーチ力不足により、その答えには辿り着けませんでした。。。それなら自分で比較して確かめてみよう!というのが、今回の記事のきっかけです。
まずは下処理から
今回は20粒の種をまく予定です。条件を分けて育てるため、まずは10粒ずつの2グループに分類しました。この段階では、どちらの種もほぼ同じような見た目をしています。

続いて、そのうち1グループの種を水に入れて吸水させます。向かって左側が吸水あり、右側が吸水なしです。この状態で一晩放置します。
一晩放置した後の種がこちら。向かって左側が吸水あり、右側が吸水なしですが、吸水ありの種の方が一回り大きくなっていることがわかります。一晩でこれだけの水分を吸収した、ということですね。
各グループから種を1粒ずつ取り出してみました。吸水ありの種(左)については、サイズが一回り大きくなったことに加えて、皮がシワシワになっていることがわかります。
種まきのコツは土に埋め過ぎないこと!?
さて、準備した種をいよいよまいていきます。依然として家庭菜園に空きスペースがないため、今回も苗床に1粒ずつまくことにしました。
ソラマメの種まきを行うにあたり、コツとなるのがこちらの写真です。種といえば土に埋めてしまうイメージですが、ソラマメの場合は写真のように一部を地上に出しておくと良いのだそうです。一部を地上に出すことで種の呼吸が促進され、発芽率が高まるのだとか。
この時、お歯黒(おはぐろ)と呼ばれる黒い部分を下にしてまくのもポイントです。ソラマメの根や芽はお歯黒から出てくるため、種まきの際はこちら側を地中に挿すようにします。

▲ソラマメのお歯黒
以上のポイントを押さえつつ、吸水あり/なしの種をそれぞれまき終えました。向かって左側の2列が吸水あり、右側の2列が吸水なしです。
発芽スピードだけで言ったら吸水ありの方が何となく早そうなイメージですが、最終的な発芽率に違いは出るのでしょうか?今回はここまでですが、芽が生え揃った頃に改めて結果をお知らせできればと思います。
◎次回の記事はこちら
(発芽率が把握できた頃に更新)