◎昨日の記事はこちら
【精霊馬・精霊牛】お盆にきゅうりの馬・なすの牛を飾るのはなぜ? - アタマの中は花畑
◎関連記事はこちら
ミソハギをお盆に供える理由は?〜名前の由来や供え方も調べてみました〜 - アタマの中は花畑
昨日に引き続き、今日もお盆に関する話題です。2年ほど前の記事でミソハギをお盆に備える理由について取り上げたのですが、お盆によく見かける植物は他にもあります。

▲ミソハギの花(参考)
そのうちの1つが、今回取り上げるホオズキです。私の実家でもホオズキを育てており、お盆の時期になると毎年供えているのですが、これには何か理由があるのでしょうか?
ホオズキ(鬼灯)の概要

科・属名:ナス科ホオズキ属
種別:多年草(品種によっては一年草扱いされる場合あり)
花色:薄黄
花期:5〜6月
原産:東南アジアなど
別名:輝血(かがち)、奴加豆支(ぬかづき)など
花言葉:偽り、ごまかし、欺瞞など
◎特徴:
ナス科ホオズキ属に属する植物の総称で、世界各地で100種類ほど分布しています。開花後に6枚の萼(がく)が急成長し、果実を包み込むことで袋状の見た目となります。
日本で一般的に知られるホオズキは東南アジア(日本では北海道〜四国)を原産とする品種で、全草に毒性を持ちます。生薬として用いられる場合もありますが、自家製のホオズキを用いるのは避けた方が良いでしょう。
また最近では、毒性のない食用ホオズキも流通し始めました。私自身はまだ食べたことがないのですが、糖度を高めたトマトのようなフルーティーな味がするようです。

たね 大和農園 食用ほおずき 種子 キャンディーランタン 小袋 PVP
お盆にホオズキを供える理由は?
ホオズキを漢字で書くと「鬼灯」となるのですが、これはオレンジ色に熟した萼・果実が提灯に見立てられたことも由来だとされています。ご先祖様の霊が乗る乗り物として精霊馬(きゅうりの馬)や精霊牛(なすの牛)が供えられることを昨日の記事でご紹介しましたが、その道のりを照らす役割を持つのがこのホオズキです。精霊棚や盆棚にホオズキを供えることにより「ご先祖様の霊が迷わずに帰ってこられるように」との願いが込められています。

このほか、ホオズキには以下のような役割があるとも言われています。いずれも欠かせない役割であり、お盆とホオズキは切っても切れない関係であることがわかります。
・家で過ごす間の仮住まいとして供える
・お供え物に彩りを添えるために供える
ホオズキの飾り方・処分方法とは?
ホオズキの飾り方は地域によってさまざまであり、特に決まった方法がある訳ではありません。また、一度に供えるホオズキの数にも特に決まりはないようです(※奇数が良いとされる場合もあります)。
①花瓶に活ける
・他の花と一緒に、花瓶などの花期に活けてお供えします。
②お盆・お皿に置く
・果物やお菓子などのお供え物と一緒に、お盆やお皿の上に置いてお供えします。
③縄で吊るす
・ホオズキの実や茎を麻紐で縛り、盆棚・精霊棚・仏壇・玄関などに吊るしてお供えする方法です。

また、お盆が終わり役目を終えたホオズキは以下のいずれかによって処分します。
・川へ流す
・土に埋める
・白い紙に包み、塩で清めてから処分する
・お寺でお焚き上げをしてもらう
私の実家でも昔は川に流していたのですが、(現在の環境では難しいため)今では別の方法で処分しています。一般的には、白い紙で包む方法、お焚き上げをしてもらう方法のいずれかが多いようです。
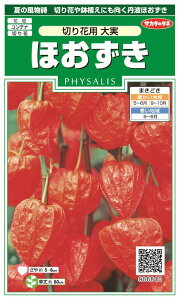
サカタのタネ 実咲 花ほおずき 切り花用 大実1袋からの採苗本数 約100本送料 6袋以上 300円 6袋未満 500円各種タネ取り合わせでご注文できます。